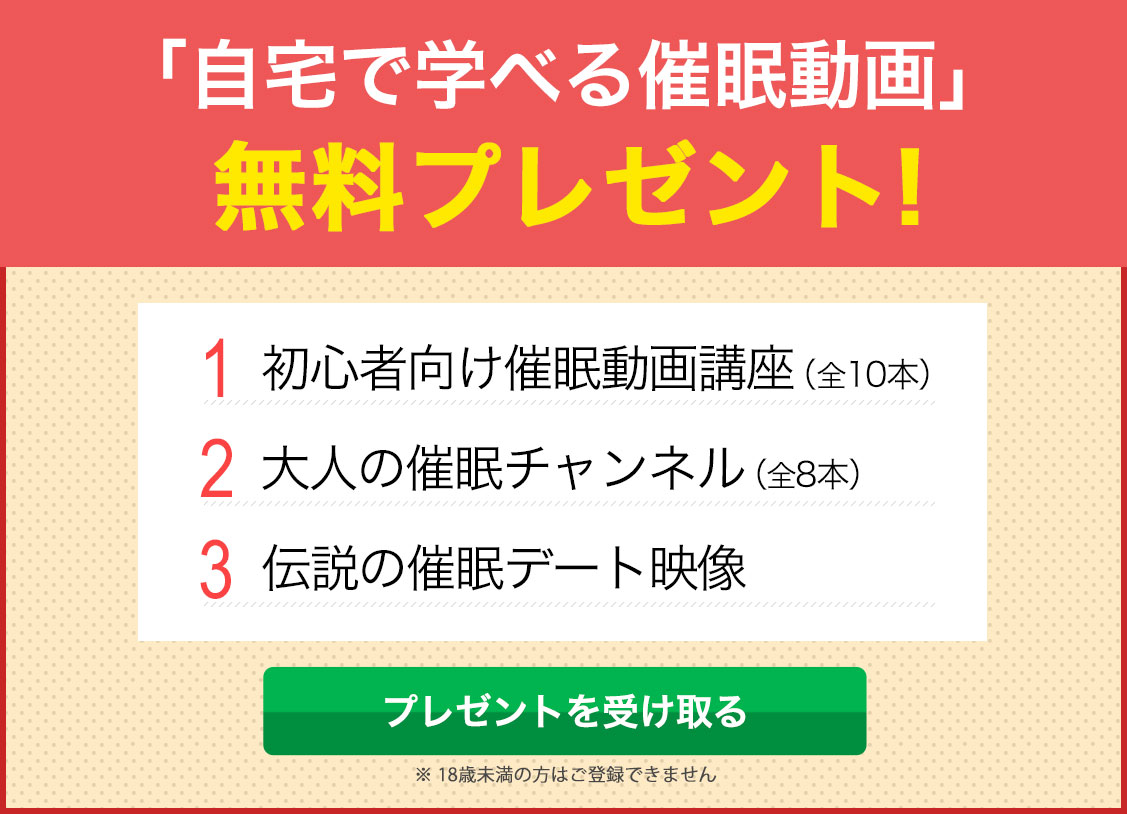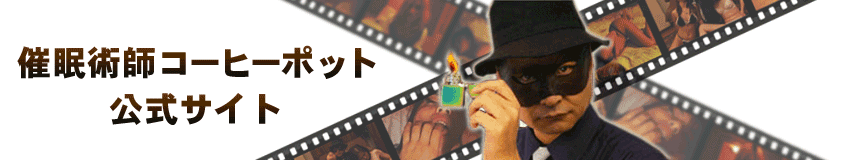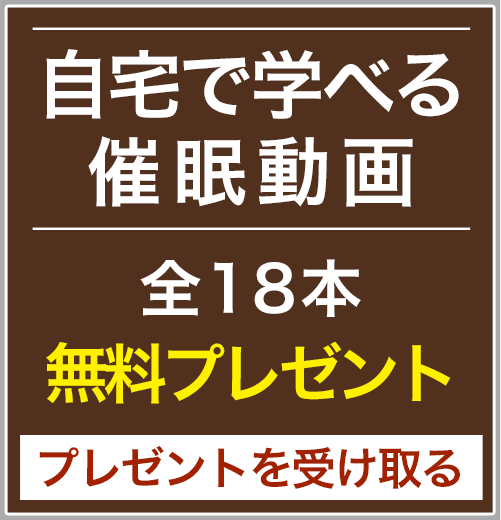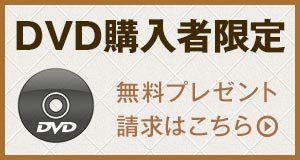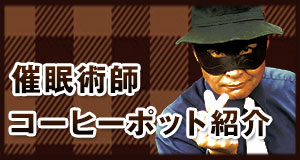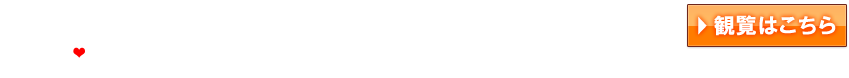幸せも免疫力も自分でコントロールできる
約20年前に出版され、話題になった書籍「脳内革命」は、近年の脳ブームのキッカケとなった書籍の一つだと言えるかもしれません。
「脳内モルヒネ」という脳から分泌させる脳内物質をテーマにしたこの本は、「脳」の未知なる可能性にワクワクとした興味を持たせてくれたように思います。
著者、春山茂雄さんが「脳内モルヒネ」と呼んでいるものは、人間の脳内から分泌されるモルヒネに似たホルモンの事。私たちは日々の生活の中で、様々な事柄を体験します。
その都度、脳内ではその体験に合わせて、色々なホルモンが分泌されているのです。
そのホルモンの数は50以上。そしてその一つ一つが私たちの身体に欠かせない役割をもっているのですが、脳の中で起きている活動は、自分では意識外のこと。
でも、これが私たちの心にも、身体にも大きな影響を与えているのです。脳の中でどのようなことが起きているのか…。
様々なホルモンの中から、今回は、「βエンドルフィン」に注目し、その効果を探ってみましょう。
脳の中では何が起きているのか?
「脳内ホルモン」「脳内物質」という言葉はよく耳にする言葉になったかもしれませんが、実はこれは正式な学術用語ではありません。
正式には「神経伝達物質」と呼ばれるものです。
人間の脳の中には数百億を超える神経細胞が存在していると言われています。その神経細胞は複雑なネットワークによって形成されています。
そして、その神経細胞同士は、シナプスによって接合されていますが、そのシナプスの間にはわずかなスペースがあります。
シナプスは前膜と後膜という、前後に異なった役割を持っています。シナプス前膜からは「神経伝達部物質」が分泌され、それをシナプスの後膜が受容します。
つまり、シナプスの前の部分で、ピッチャーが投げたボール(神経伝達物質)を、シナプスの後ろ側にいるキャッチャーが受け取ることで、情報伝達ができるのです。
この神経伝達物質が俗称として「脳内物質」と呼ばれています。
ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン、セロトニン、メラトニン、アセチルコリン、エンドルフィンなど様々な脳内物質があり、その種類は50以上。
それぞれが私たちの感情やモチベーションなどを左右する重要な物質なのです。ストレスを感じたり、痛みを感じたり、怒りや悲しみを感じたとき、脳内でその出来事から体と心を守るために、神経伝達部室を分泌させるのです。
つまりは、体を元気にさせるため、体を守るために、私たちの身体が自然に対応してくれているものなのです。
先にあげた「脳内モルヒネ」は、様々な脳内物質の中でも人を楽しくするホルモンのことを指しています。いわゆる快楽ホルモンが、「脳内モルヒネ」なのです。
そして、その中でも、特に効力のある物質が「βエンドルフィン」だと言われています。
さて、今度はその「βエンドルフィン」について探っていきましょう。
幸福になれる魔法のホルモン―βエンドルフィン
βエンドルフィンは、3種類あるエンドルフィンの中のひとつです。
エンドルフィンには、α(アルファ)、β(ベータ)、そして、γ(ガンマ)エンドルフィがあります。その中でも、特に苦痛を取り除くときに多く分泌されるのが、βエンドルフィンです。
βエンドルフィンが「脳内モルヒネ」「脳内麻薬」と呼ばれている理由は、その鎮痛効果にあります。βエンドルフィンには、モルヒネの6.5倍の鎮痛効果があるといわれているのです。
「ランナーズハイ」という状態を作り出しているのも、このβエンドルフィンだと言われています。ランナーが苦しい状態で走り続け、ストレスのかかった状態が一定時間続くと、そのストレスから身を守るために、βエンドルフィンが分泌され、ストレスが軽減。
さらには、快感や陶酔感を与えてくれるのです。このことによって、ランナーは苦しさから解放され、恍惚感を覚えます。
マラソンがクセになるというのは、その快感を味わった人が、また同じ感覚を体験したいという思いから生じるのです。
つまり、ストレスなどから身を守る鎮痛効果と、多幸感を感じさせるという点が、βエンドルフィンの効果です。
医療で使用されるモルヒネは、鎮痛作用はありますが、同時に依存性や副作用の危険性があります。一方、私たちの脳内から分泌される脳内モルヒネ、βエンドルフィンには、その心配はありません。
また同時に、このβエンドルフィンは免疫力高め、病気への抵抗力をつけるという力があることもわかっています。
これは癌と闘う免疫機能の担う「NK活性」を高める作用もあり、抗癌作用も確認されているのです。
ここまでの説明を見ていると、エンドルフィンが分泌されるときは、怪我をしたり、辛い体験をしたりと、ある程度のストレスを感じることで分泌されるように見えますが、実は、βエンドルフィンは、リラックスした状態でも分泌されることが分かっています。
美味しいものを食べているときやヨガや瞑想をしているときなど、リラックスした状態でもβエンドルフィンは分泌され、幸福感を与えてくれます。
病気からの免疫力を高めること同様に、脳を休め、注意・集中力、記憶力、創造性など、脳の機能を高めてくれる作用があると言われています。
まさに、βエンドルフィンは、私たちを幸せにしてくれる魔法のホルモンなのです。
心も体もハッピーになる方法
この魔法のホルモンはどうしたら作り出すことができるのでしょうか。
その方法は意外と簡単です。
先にあげたように、リラックスした状態でβエンドルフィンが分泌されるのですから、リラクスした状態を作りだせばいいのです。
大自然の景色を見たり、好きな音楽を聴いたり、ヨガや瞑想、アロマやお香なども効果的でしょう。また、刺激や苦痛に対しても分泌される特性から、多少のストレス状態を作りだすことでも可能です。
例えば、マラソンをはじめとする少し負荷が持続するような運動や、刺激を与える辛い料理を食べる、少し熱めのお風呂に入る、というような行動でもβエンドルフィンを分泌させることができます。
「脳内モルヒネ」は“人の気分をよくするだけでなく、老化を防止し自然治癒力を高めるすぐれた薬理効果がある” と春山茂雄さんは書いています。
また“どんな薬にもかなわない優秀な製薬工場を体内にもっている”とも言っています。βエンドルフィンの分泌によって、私たちは多幸感を感じ、免疫力が高まり、脳の機能も活発化する。
私たち人間は他のものに頼らずとも、自らの力によって幸福感とともに、健康に生きていける体をもっていることもわかってきました。
優秀な製薬工場の存在を知った今、それを多いに利用しない手はないのかもしれません。